原宿駅前に突如として登場し、多くの注目を集めた「イケア原宿」。手軽に北欧デザインに触れられる新しい空間として親しまれてきましたが、2024年末をもって閉店するというニュースが話題を呼んでいます。なぜ、わずか4年で幕を閉じることになったのでしょうか?本記事では、イケア原宿の開業から閉店までの背景、都心型店舗の課題、そして今後のIKEAの戦略について詳しく解説します。この記事を読めば、単なる閉店ニュースの裏にあるビジネスのリアルが見えてくるはずです。
イケア原宿の閉店ニュースが話題に
原宿店の開業から閉店までの流れ
イケア原宿は、2020年6月に東京都渋谷区・原宿駅前にオープンしました。イケアとしては初の「都心型小型店舗」という新しい挑戦で、従来の大型郊外店とは異なるコンセプトでした。開業当初は新しい試みに注目が集まり、SNSやメディアでも大きく取り上げられました。場所もJR原宿駅の目の前という好立地で、多くの若者や観光客で賑わっていたのです。
しかし、2024年末に突如「閉店」のアナウンスがあり、利用者やファンの間で衝撃が走りました。わずか4年という短い営業期間での撤退は、異例の判断といえるでしょう。閉店は2024年12月31日をもって正式に行われました。イケアがこれまでに出店してきた中でも、短命な店舗のひとつとなってしまいました。
この流れを振り返ると、イケア原宿は新しいビジネスモデルの実験場であったと同時に、都心での展開における課題も浮き彫りにした事例といえます。
SNSでの反応と世間の驚き
閉店のニュースが発表されると、X(旧Twitter)やInstagramでは「えっ!?原宿のイケア閉店するの?」「気軽にIKEAの雑貨を買える場所がなくなる…」といった驚きの声が多数投稿されました。特に若者世代や学生、一人暮らしを始めたばかりの人たちにとっては、気軽に立ち寄れる店舗だっただけに、その衝撃は大きかったようです。
また、「原宿のイケアはカフェだけでもよく利用してた」という声や、「観光で行ったときの楽しみの一つだった」という口コミも多く見られました。イケア原宿の店内にはスウェーデン風の軽食を楽しめるカフェが併設されており、家具や雑貨だけでなく“体験”としても評価されていたのです。
SNS上で特に目立ったのは「短すぎた営業期間への疑問」です。「なぜこんなに早く閉めるの?」「うまくいってるように見えたのに」といった、閉店の背景に関心を寄せる声が相次ぎました。
小型店舗としての実験的な試み
イケア原宿は「IKEA City Shop」として、従来の郊外型の大型店とは異なる形態で運営されていました。売場面積は約2,500平方メートルと、船橋や立川にある大型店舗の1/10以下。商品のラインナップも日用品や雑貨、小型家具に絞られており、大型家具や倉庫スペースはありませんでした。
この業態は、都市部の消費者が「気軽に立ち寄って、気に入ったらECで購入する」という購買行動に対応するためのものでした。また、店舗内には商品の展示に加えて、スウェーデンフードの軽食コーナーもあり、都心でIKEAの“世界観”を手軽に体験できる空間づくりがされていました。
こうした取り組みは、特にコロナ禍の中で「買い物スタイルの多様化」を模索する中での実験的な試みでした。ただし、この実験がうまくいったかどうかには賛否両論があり、今回の閉店はその結果のひとつと見ることもできます。
コロナ禍が与えた影響
2020年のオープンはまさに新型コロナウイルスが猛威を振るっていた時期と重なりました。原宿という立地は本来、観光客やショッピング客でにぎわうエリアですが、当時は外出自粛やインバウンドの減少などで人通りが大きく減少していました。
また、感染対策のために店舗の運営にも制限がかかり、フードスペースの一部閉鎖や時短営業も実施されていました。その影響で、期待していたような“人の流れ”が生まれにくかった可能性があります。
さらに、都心のオフィス街ではテレワークが浸透し、人流の変化が顕著になりました。原宿も例外ではなく、平日の来店者数が伸び悩んだとの報道もあります。コロナ禍という“不可抗力”が、イケア原宿の成功に大きな影を落としたと言えるでしょう。
なぜ「原宿」だったのか?
イケアが都心型店舗の第1号として「原宿」を選んだ背景には、いくつかの理由があります。まず、原宿はファッションやカルチャーの発信地であり、若者や外国人観光客に人気の高いエリアです。トレンドに敏感な人々が集まるこの場所で、新しいIKEAの形を試すのは理にかなっていたとも言えます。
また、原宿駅前という立地は、駅の改札を出てすぐという圧倒的なアクセスの良さが魅力でした。駅ビル「WITH HARAJUKU」の商業施設内に出店したことで、他のブランドとの相乗効果も狙えました。
IKEA側は、原宿を「ブランド体験の場」と位置づけ、売上だけでなく、ブランドのイメージ向上や都心顧客のニーズのリサーチなども目的としていたようです。つまり、単なる売場ではなく、情報発信と実験の場としての役割が大きかったと言えるでしょう。
イケア原宿のビジネスモデルとは?
通常店舗との違い
イケア原宿は、通常のイケア店舗とは大きく異なる特徴を持っていました。最大の違いは「店舗の規模」です。たとえば、イケア港北(神奈川)や立川(東京)のような大型店では、広大なフロアを活かし、展示スペースと倉庫を一体化した売場構成になっています。一方、原宿店は小型店舗であり、売場面積が非常に限られていました。
このため、原宿店では大型家具の展示や販売はほとんど行っておらず、主に「キッチン雑貨」「収納アイテム」「照明」「観葉植物」「テキスタイル」など、持ち帰りしやすい商品に特化していました。また、倉庫スペースがないため、大型家具の購入はQRコードを使ってオンラインで注文し、自宅配送するスタイルが主流でした。
つまり、イケア原宿は「体験型+オンライン誘導型」のハイブリッド店舗としての役割を果たしており、従来の“倉庫一体型の大規模店舗”とは異なる、新しいビジネスモデルの一環だったのです。
都心型小型店舗という新戦略
イケア原宿は、IKEAがグローバルで推し進めている「都心進出戦略」の一環として登場しました。この戦略は、都市部の限られたスペースで、より多くの人にブランド体験を届けることを目的としています。特に日本のように、クルマを持たない若者が多く、郊外まで行くのが難しい国では、都心型小型店舗のニーズは高まると見込まれていました。
この戦略の背景には、「より身近なIKEA」「日常生活に溶け込むIKEA」を目指すという方向性があります。駅近、タワマン近く、商業施設内など、人の流れが多い場所で、生活雑貨を中心に展開することで、IKEAの“敷居の高さ”を取り払おうとしたのです。
しかし、このモデルは簡単ではありません。スペースの制約、商品数の制限、人件費や賃料の高さなど、都心ならではの課題も抱えており、原宿店はその試金石的な存在でもありました。
商品構成とターゲット層
原宿店の商品構成は、日常使いできるアイテムが中心でした。特に注目されたのは以下のような商品群です:
| カテゴリ | 具体例 |
|---|---|
| キッチン用品 | マグカップ、フライパン、食器セットなど |
| インテリア雑貨 | クッション、キャンドル、ランプ類 |
| ストレージ用品 | 収納ボックス、衣類収納ケース |
| 観葉植物 | 小型のフェイクグリーン、本物の鉢植えなど |
| テキスタイル | タオル、寝具カバー、ラグなど |
ターゲット層は明確に「都心で暮らす若年層」や「原宿を訪れる若者・観光客」でした。価格帯もリーズナブルで、大学生や新社会人、若いカップルなどが“気軽に衝動買いできるラインナップ”が中心でした。
また、カフェスペースではスウェーデンミートボールやベリースムージーなど、手軽に楽しめるメニューが並び、IKEAらしさを感じられる体験が可能でした。このように、「見て・買って・味わって帰る」ワンストップ体験ができる構成となっていました。
売上と集客の課題
イケア原宿は多くの人に注目される一方で、「売上」と「集客」という点では課題を抱えていた可能性があります。まず、店舗面積が限られていたため、取り扱える商品数が少なく、客単価を上げにくい構造となっていました。
また、原宿という場所柄、平日は人通りが比較的少なく、週末や祝日に人が集中する傾向がありました。つまり「安定した来客」が期待しにくい環境だったとも言えます。さらに、都心の店舗は固定費(賃料や人件費)が非常に高いため、収益を確保するにはそれ相応の売上が求められます。
その上で、原宿店は大型家具の即時販売ができず、ほとんどの商品は持ち帰り可能な小型品が中心でした。家具という高単価商品の売上比率が低く、単価の低い雑貨中心での運営は、ビジネスモデルとして持続可能ではなかった可能性があります。
他店舗との比較
他のイケア店舗、たとえば「IKEA渋谷」や「IKEA新宿」との比較でも、原宿店の特徴と課題が見えてきます。渋谷店はコンパクトながらも家具の展示スペースが多く、商品のバリエーションも豊富。一方で、新宿店はより実用性重視で、生活動線に沿った提案がされており、働く世代へのアプローチが強い印象です。
対して原宿店は「若者向け・観光客向け・ブランド体験型」にフォーカスしすぎたため、リピーターを生み出しにくかったとも考えられます。特に生活導線からやや外れた“観光立地”という点が、日常的に使う店としての定着を妨げた可能性があります。
また、渋谷・新宿に比べると、買い物後に荷物を持ち帰る導線が不便だったという声も少なくありませんでした。このように、立地・商品・ターゲットすべてにおいて、他店舗とは異なる方向性で勝負していたことが、閉店という結果に繋がったとも考えられます。
閉店の本当の理由は?公式発表と憶測
イケアの公式発表を検証
イケア原宿の閉店について、イケア・ジャパンは公式に「今後の事業戦略の見直しの一環」として閉店を決定したと発表しています。この説明はとても一般的な表現で、具体的な数値や理由は公表されていませんでした。そのため、多くのメディアやユーザーは「実際のところ何が原因だったのか?」と深く掘り下げようとしました。
イケアはもともと、都心での出店により、より多くの顧客にアプローチするための新戦略を進めてきました。しかし、原宿店はその戦略の初期段階にあったため、ある意味では「実験的な位置づけ」であったと考えられます。
実際、IKEA側の広報も「今後の事業戦略におけるバランスを再考する必要があった」とコメントしており、戦略的撤退だったことを匂わせています。つまり、失敗というより「方向転換」としての閉店という色合いが強く、今後に向けた再構築の一部とも読み取れます。
家具販売の都心展開の限界
IKEAの主力商品は、ベッドやソファ、収納棚などの“大型家具”です。しかし、都心型店舗ではこれらを十分に展示するスペースがありません。さらに、購入後の持ち帰りが困難なため、多くの顧客はその場で購入を決めず、ECサイトを通じて後日注文するという流れが多かったのです。
このような構造では、商品の訴求力が弱まり、衝動買いや比較購入が難しくなります。さらに、家具は“見て・触って・試して”から購入する人が多いため、狭い展示スペースでは十分な体験ができません。その結果、販売機会を逃すことが増えてしまいます。
また、都心では生活空間が限られており、大型家具のニーズ自体も低い傾向があります。こうした背景から、原宿のような小規模な都心型店舗では、イケアの本来の強みを活かしきれないというジレンマがあったのです。
コスト面の問題とは
イケア原宿が立地していたのは、原宿駅前の「WITH HARAJUKU」という再開発商業ビルです。ここは、表参道や竹下通りからも近く、都内でも屈指の一等地。そのため、賃料は非常に高額であることが予想されます。
また、店舗運営には多くの人件費がかかります。原宿のような人気エリアでは人材確保も難しく、人件費はさらに高騰する傾向があります。それに加えて、コロナ禍による来客数の変動や、インバウンドの激減など、安定した収益が見込めない要素が多く存在していました。
さらに、物価上昇や輸送コストの増加など、2022年以降に広がった「コストプッシュ型の経済環境」も店舗経営に影響を与えたと考えられます。高コスト体質の都心型店舗は、利益率が低く、撤退判断も比較的早く下される傾向があります。原宿店も例外ではなかったのでしょう。
人流の変化と影響
原宿は、若者を中心に多くの観光客が訪れる「人の流れが多いエリア」として知られています。しかし、2020年以降のコロナ禍、そしてその後のテレワーク・リモートワークの定着により、平日昼間の人流が大きく変わってきました。
かつてのように、買い物客や観光客が平日でも多く訪れるような状況ではなくなり、週末や祝日だけが混雑する「偏った来客パターン」になってしまったのです。こうした状況では、日々の売上が安定せず、効率的な店舗運営が難しくなります。
また、原宿周辺は新しい商業施設や飲食店の出店・撤退が激しく、競合も多いため、常に新しい魅力を提供し続けなければ埋もれてしまいます。イケア原宿は開業当初こそ話題を集めましたが、リピート客の獲得や新規客の呼び込みには限界があったのかもしれません。
閉店は成功か失敗か?
閉店という結果だけを見ると、「失敗だった」と考えがちですが、ビジネス的には一概にそうとは言い切れません。イケア原宿は、“都心型小型店舗モデルの実験場”としての役割を持っていたとも言われており、ここで得たデータや知見は、今後の事業展開に活かされるはずです。
たとえば、「若年層はどんな商品に興味を持つのか?」「都心の雑貨需要はどの程度あるのか?」「小型店でもブランド体験が届けられるのか?」といったテーマについて、実店舗を通じてリアルな反応を得ることができました。これこそがイケア原宿の“成功”の側面です。
つまり、商業的には赤字だったとしても、マーケティングやブランディング、今後の戦略立案という観点では、十分に意義があったとも言えるのです。閉店は「失敗」ではなく「役割を終えたプロジェクトの終了」と考えるのが、より正確な評価かもしれません。
今後のIKEAの戦略と方向性
都心型店舗の見直しはあるか?
イケア原宿の閉店を受けて、多くの人が気になったのが「都心型店舗モデルそのものが失敗だったのか?」という点です。結論から言うと、イケアは都心型店舗を完全に否定しているわけではありません。むしろ、原宿店で得られたデータや課題を踏まえ、より柔軟な形で進化させる可能性が高いと見られています。
たとえば、渋谷店や新宿店は営業を継続しており、今後も運営が続けられる予定です。これらの店舗では、原宿よりも生活導線に近い立地に出店しており、家具だけでなく、収納や整理用品といった日用品のニーズにうまく応えています。
今後のイケアは、「小型店舗=原宿のような観光型」ではなく、「生活密着型」「暮らしに寄り添う立地選定」がカギになると考えられます。また、無理に“店舗で売る”のではなく、ECサイトと連携させながらブランド体験を重視する新たな店舗設計も模索されるでしょう。
EC(オンライン販売)へのシフト
近年のイケアは、明確に「オンライン販売」へと軸足を移しつつあります。日本国内でも、2020年以降にECサイトが大幅に拡充され、自宅にいながら商品を選び、配送・組み立てまで依頼できるサービスが整いました。
都心部ではとくに、家具を“見て即決”するよりも、Webで調べて比較検討し、ネットから購入するユーザーが増えています。そのため、小型店舗は「ショールーム的な役割」を担い、オンラインへと送客するのが理想的な形だと言えます。
イケア自身も、EC強化を世界戦略の一つとして掲げており、AIやAR(拡張現実)技術を使った「自宅で家具配置を試せるアプリ」なども展開中です。これらのデジタルツールと、都心型店舗を融合させることで、新たな購買体験を提供する試みが進行中です。
イケア原宿の閉店も、こうしたオンライン移行への加速の一環と捉えることができます。
他国の都心型店舗の現状
イケアは世界中で「都心型店舗モデル」を展開しています。たとえば、ニューヨークの「IKEAプランニングスタジオ」や、パリ、ロンドン、マドリードなどの主要都市にも同様の店舗が存在しています。これらの都市では、「展示と相談に特化したミニマルな店舗」が一定の成果を上げています。
これらの成功事例に共通しているのは、「家具をその場で売らない」という点です。代わりに、プランニング(設計相談)や、生活空間の提案、オンライン注文を前提とした接客に特化しています。また、店舗数も少なく、地域に合わせた戦略を緻密に展開しています。
日本の原宿店は、「観光地立地」+「若者ターゲット」という少し特殊なポジションだったため、上記のような成功例とは事情が異なります。今後、日本国内でも、海外事例を参考に「生活提案型×オンライン連携型」の都心モデルに再設計される可能性が高いです。
サステナブルなビジネス展開
イケアは近年、サステナブル(持続可能)な取り組みに非常に力を入れています。再生素材の活用、省エネ商品の開発、家具のリユース・リサイクルなどを積極的に推進しています。都心型店舗でも、その姿勢は一貫しており、原宿店でも「サステナブルな暮らしを始めるきっかけを提供する」展示や商品提案が行われていました。
今後のイケア戦略では、このサステナブル路線がさらに強化されると見られています。たとえば「家具のサブスクリプション(定額利用)」や、「不要家具の回収・再販売」など、モノを“売る”だけではないビジネスモデルへの転換が加速しています。
都心型店舗でも、単なる物販から「循環型ライフスタイルの提案拠点」へと進化させることで、新たな顧客層の獲得が期待されます。こうした姿勢は、若者や都市生活者にも共感を得やすく、ブランド価値の向上にもつながります。
顧客との新たな接点作り
今後のイケアは、「店舗×デジタル×体験」の3軸で、顧客との新たな接点作りを進めていくと考えられます。特に注目されているのが、以下のような取り組みです:
- アプリを使った買い物サポート:在庫確認・家具の配置シミュレーション・AR機能など
- イベント型体験の提供:期間限定のポップアップストアやワークショップ開催
- パーソナライズされた提案:過去の購入履歴や好みに応じた商品提案
- SNSとの連動:InstagramやPinterestでのインテリア事例の共有
- BtoB提案の強化:飲食店やオフィスなど法人への家具提案
こうした多角的な接点を通じて、IKEAブランドの「暮らしに寄り添うパートナー」としての価値を高めていく方針です。単なる家具販売業ではなく、“暮らしのプラットフォーム”として成長していくことが、今後の鍵を握ります。
閉店後の原宿店の跡地はどうなる?
原宿駅前という好立地
イケア原宿が入居していたのは、JR原宿駅の目の前にある商業施設「WITH HARAJUKU(ウィズ原宿)」の1階部分。この場所は原宿の“顔”ともいえる好立地で、駅の改札を出てすぐ、さらに表参道や竹下通りにも接続しており、都内でも有数の一等地です。
この立地は、ショッピング・観光・カフェ・アパレルなど、多様な業態にとって非常に魅力的であり、イケアの撤退後もすぐに別のテナントが入る可能性が高いと言われています。実際、WITH HARAJUKU内にはユニクロや無印良品など人気ブランドが既に入居しており、施設全体としての集客力は健在です。
そのため、跡地には再び大手ブランド、もしくはZ世代をターゲットにした“話題性のある企業”が出店する可能性が高いでしょう。場所のポテンシャルは非常に高く、イケアの撤退によってその価値が下がることはほぼないと考えられます。
テナント候補と噂
イケア原宿の閉店が発表されると同時に、「次にどんな店が入るのか?」という憶測がSNSや業界内で飛び交いました。いくつかの有力候補として挙げられているのが以下のようなブランドや業態です。
| 業態カテゴリ | テナント候補の例 |
|---|---|
| カフェ・飲食 | スターバックス リザーブ、ブルーボトル、タリーズ旗艦店など |
| ライフスタイル | ニトリデコホーム、Francfranc、Flying Tigerなど |
| ファッション | ZARA HOME、ユナイテッドアローズ系列、韓国系ファッションブランド |
| デジタル系 | Apple Storeミニ、無人コンビニ、ガジェット体験型ショップ |
とくに「映える空間」を意識したブランドの出店が期待されており、TikTokやInstagramなどで話題性を生むような“空間マーケティング”を展開する企業が注目されると予想されています。
また、「ポップアップショップとして活用される可能性」もあります。期間限定で話題の商品を展開するフレキシブルなスペースとして使われることで、原宿のトレンド発信地としての役割がより強化されるでしょう。
地域経済への影響
イケア原宿の閉店は一部のファンにとって残念なニュースでしたが、地域経済全体への影響はそれほど深刻ではないと考えられます。理由は、原宿というエリアがもともと観光・ショッピングの中心地であり、多くの人気ブランドや施設が密集しているためです。
むしろ、イケアが占めていた大きなスペースに新たなテナントが入ることで、周辺の人流が活性化する可能性すらあります。例えば、話題性の高いカフェや体験型ショップが入れば、再び原宿駅前が“人を集めるハブ”として注目されることも期待できます。
また、WITH HARAJUKU自体が多層階構造で、複数のブランドが連携して集客する設計になっているため、1テナントの入れ替えは長期的な経済には大きなマイナスにはなりにくいのです。
若者文化と原宿のこれから
原宿は、長年にわたって若者文化の発信地として成長してきました。竹下通りの原宿ファッション、キャットストリートのカフェ文化、表参道のラグジュアリー路線など、ジャンルの異なる文化が共存しているのが特徴です。
イケア原宿も、その流れの中で「新しい暮らしの形」を提案する店舗として一定の役割を果たしていました。しかし、現在の若者は「物を買う場所」よりも「体験を共有できる場所」を求める傾向が強くなっています。つまり、ただ商品を陳列するだけの店舗ではなく、空間・コンセプト・写真映え・限定性といった要素が重視されるのです。
そのため、イケア跡地には「体験型」「ストーリー性のある」ブランドが求められるでしょう。原宿のこれからを担うのは、こうした時代の空気を読み取った“次世代型テナント”なのかもしれません。
IKEAの空白をどう埋めるか?
イケア原宿がなくなった今、その空白をどのように埋めるかが課題になります。これには2つの側面があります。ひとつは「イケアの利用者に対する対応」、もうひとつは「原宿というエリアに対するブランド価値の再構築」です。
まず、イケアを日常的に使っていた人たちには、渋谷店・新宿店・立川店といった近隣店舗や、公式オンラインショップの活用が推奨されています。とくに最近はアプリでの購入や、バーチャル内覧機能も充実しているため、買い物の不便さはかなり解消されてきています。
一方で、原宿という場所に空いた「北欧デザインの暮らし提案」の空間は、他のブランドが引き継ぐか、新たな形で埋めていく必要があります。今後は、サステナブル・ミニマル・ボーダレスといった価値観を背景にしたブランドが、その空白を自然に埋めていくことになるでしょう。
まとめ:イケア原宿の閉店が教えてくれたもの
イケア原宿の閉店は、多くの人にとって驚きと共に受け止められました。原宿駅前という好立地、IKEA初の都心型小型店舗という注目の形態、オープンからわずか4年での撤退。この一連の流れは、ただの閉店ニュースにとどまらず、「都市におけるライフスタイル提案型ビジネスの難しさ」や「コロナ禍による消費行動の変化」を象徴しているとも言えます。
小型店舗という新たな挑戦は、スペースや商品構成に制限がある中で、どれだけブランド体験を届けられるかという大きな課題と直面していました。また、原宿という“観光と若者文化”の中心地では、リピーターを獲得しにくいという立地的な難しさも浮き彫りになりました。
一方で、イケアがここで得た知見やデータは、今後の事業戦略にとって非常に貴重なものです。今後は、ECとリアルをつなぐハイブリッドモデルの進化、サステナブルな提案型店舗の展開、体験を重視したブランド戦略が加速していくと予想されます。
イケア原宿の跡地には、新たな文化の発信拠点となるような次世代型の店舗が登場する可能性が高く、原宿エリア自体の進化にも注目です。短命だったイケア原宿ですが、その存在は「都市における暮らしと商業の未来」を考えるうえで、大きな意味を持っていたのです。

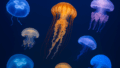
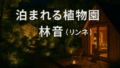
コメント