「この味が恋しくなる——」そう語るファンも多い天下一品。こってりスープで全国的に知られるこのラーメンチェーンが、近年“閉店ラッシュ”という現象に直面しています。なぜ愛され続けたブランドが、次々と店をたたんでいるのでしょうか?その背景には、ラーメン業界全体を揺るがすさまざまな課題と、天下一品ならではの戦略の転換がありました。この記事では、天一の閉店が相次ぐ理由から業界の動向、そして今後の展望までを徹底的に掘り下げていきます。
天下一品の閉店が相次ぐ背景とは?
天下一品の店舗数の変遷と閉店傾向
天下一品は、1971年に京都で創業して以来、「こってりラーメン」の代名詞として全国に店舗を広げてきました。しかしここ数年、特に2023年頃から閉店する店舗が目立つようになりました。ピーク時には240店舗以上を展開していましたが、2024年には220店舗を下回る地域もあり、一部地域では「近所の天一がなくなった」という声も増えています。
この閉店傾向は一時的なものではなく、計画的なリストラや業績不振による撤退も含まれていると考えられています。実際に、地方都市での集客減や、古くからのフランチャイズ店舗の更新契約を見送るケースが増えているのです。天一ファンにとっては残念なニュースですが、時代の流れとともに見直しが迫られている部分も多いと言えるでしょう。
閉店が目立つ地域の共通点
閉店が特に目立っているのは、地方都市や郊外エリアです。これらの地域では、以前は車での来店客が多く、地元住民の食生活に深く根付いていました。しかし、近年の若年層の外食離れや健康志向の高まりにより、こってりラーメンへのニーズが低下してきています。
また、地方都市では人手不足の影響も深刻です。特に厨房オペレーションの難しさや、独特なスープ製造の工程が敬遠され、アルバイトが集まりにくくなっているのです。こうした複合的な理由が、地方店舗の経営継続を難しくしているのです。
本部の方針転換とその影響
天下一品本部では、ブランドイメージの再構築や直営店への集中戦略を進めているといわれています。つまり、フランチャイズに頼らず、品質管理が行き届いた店舗運営を強化する流れです。このため、利益率の低いフランチャイズ店舗や古い契約形態の店舗に対し、契約更新を見送るケースが増加しているのです。
こうした本部の方針転換は、短期的には店舗数の減少を招きますが、長期的にはブランドの安定と品質向上を目指す戦略と捉えることもできます。ただし、愛着ある店舗が急に閉店することで、ファン離れが進むリスクも否定できません。
フランチャイズ契約の問題点
天下一品は長年、フランチャイズ方式での出店を中心に展開してきました。しかし、近年はその契約形態にも見直しの必要が出てきています。例えば、材料費やスープの仕入れ価格が上昇する中、ロイヤリティを含めた経費が重くのしかかり、オーナー側の収益が圧迫されています。
また、契約年数が長期にわたる場合、新しい経営手法に対応できず、時代遅れのサービスや店舗づくりが続くケースもあります。結果として地域のニーズとマッチせず、売上が減少し、閉店という選択を迫られてしまうのです。
SNSでの反応と消費者の声
SNS上では、「あの天一が閉店してショック」「こってりが恋しいのに…」といった声が多く見られます。特にX(旧Twitter)では、閉店情報が投稿されるたびにトレンド入りすることもあり、一定数の熱狂的ファンが存在することがわかります。
一方で、「最近味が落ちた気がする」「昔より高くなった」といった否定的な意見もあり、消費者の目が厳しくなっていることも事実です。こうした反応を丁寧に汲み取り、改善に活かせるかどうかが、今後のブランド維持に大きく関わってくるでしょう。
ラーメン業界全体が直面している課題
原材料価格の高騰と経営圧迫
飲食業界全体で深刻化しているのが、原材料価格の高騰です。ラーメンに欠かせない小麦粉、豚骨、鶏ガラ、油などの価格は、国際的な需給バランスや円安の影響で大幅に上昇しています。これにより、天下一品のような個性的なスープを使う店舗では、原価率が大きく跳ね上がっているのです。
さらに、スープの製造には特別な工程と時間が必要なため、簡単にコストカットができません。このため、値上げか品質の妥協かというジレンマに陥ってしまうのです。結果的に、価格に敏感な顧客層が離れていくリスクも高まっているのです。
人手不足と営業時間の短縮
飲食業界にとってもう一つの大きな課題は、人手不足です。特に深夜営業や24時間営業を行っていた店舗では、スタッフの確保が難しくなり、営業時間の短縮を余儀なくされるケースが増えています。
天下一品でも、かつては夜遅くまで営業していた店舗が、現在では21時閉店などにシフトしています。これにより、仕事帰りに立ち寄るサラリーマン層や、深夜の〆ラーメンとしての利用が減少し、売上減少にもつながっています。
外食離れとテイクアウトの増加
コロナ禍をきっかけに、外食から中食(持ち帰り)へのシフトが加速しました。天下一品もテイクアウトメニューを充実させていますが、「こってりスープ」の特性上、時間が経つとクオリティが下がってしまうという問題があります。
そのため、他のラーメンチェーンやデリバリー向きの店舗に比べて不利な状況が続いています。テイクアウトでも店内同様の満足度をどう確保するかが、大きな課題となっています。
他ブランドとの競争激化
近年では、「一蘭」「一風堂」「らぁ麺 はやし田」など、洗練されたラーメンを提供するブランドが増えています。また、家系ラーメンや淡麗系ラーメンといったトレンドも次々と生まれ、消費者の好みも多様化しています。
こうした中で、天下一品の「超こってり系」は好みが分かれるため、広範囲な層に訴求するのが難しくなっています。リピーターを増やすには、味やサービスのアップデートも求められています。
地方と都市部での差異
地方では車社会によるアクセスの良さから郊外型店舗が定着していましたが、都市部では地価や人件費の高さが経営を圧迫しています。さらに、都市部の若年層は健康志向が強く、脂っこいラーメンを避ける傾向もあるため、都市型店舗は苦戦しているのです。
このように、地域ごとの需要や経済状況に柔軟に対応できないと、競争に取り残されてしまうリスクが高まっているのです。
天下一品の味とスタイルの変化はあったのか?
昔と今の「こってり」の違い
天下一品といえば、スプーンが立つともいわれる「こってり」スープが最大の特徴です。しかし、近年「昔のほうがもっと濃厚だった気がする」「味が薄くなった?」と感じるファンも少なくありません。
実際、味に微妙な変化があったのは事実です。スープの品質は本部からのセントラルキッチンで一定に保たれているものの、店舗ごとの調整や地域性による味のバラつきが発生しています。また、健康志向を意識してか、以前よりも脂分を抑えたマイルドな味付けに変更されたという声もあります。
さらに、原材料費の高騰や調理工程の簡素化など、経営上の都合でスープの濃度が調整されることもあります。その結果、「昔のこってりをもう一度食べたい」というコアファンの声が増えているのです。
地域ごとの味のバラつき
天下一品は全国に展開しているため、地域ごとの嗜好に合わせて若干の味調整がされていることがあります。特に、関西圏と関東圏では「こってり」の濃さやとろみの強さが微妙に異なるといわれています。
これは、各店舗で提供される「こってり」スープが、完全に同一ではなく、店舗での加熱や濃度調整によって違いが出るためです。つまり、スープ自体は本部から提供されても、最終的な仕上がりは各店のオペレーションに依存する部分があるのです。
また、フランチャイズ店舗ではオーナーの裁量でトッピングやサイドメニューが異なる場合もあり、統一感に欠ける印象を持つお客様もいます。これが味のブレにつながり、「味が変わった」と感じられる原因の一つとなっています。
メニュー改定の影響
天下一品では定期的にメニューの見直しが行われています。例えば、近年では「屋台の味」や「こっさり」といった新たな味のバリエーションが追加され、より多様な層へのアプローチが進められています。
しかし、このメニュー改定によって「昔ながらのこってり一本勝負」がブレてしまったという印象を持つ人もいます。特に年配のファンにとっては、「昔のあのこってりだけで勝負していた頃が良かった」という声も根強くあります。
また、新メニュー追加により、厨房オペレーションが複雑になり、主力商品の味や品質にまで影響を与えているという指摘もあります。特に新人スタッフが多い店舗では、調理ミスによって味にばらつきが出やすくなるという懸念もあるのです。
客層の変化とその背景
かつての天下一品は、学生やサラリーマンを中心に、「ガッツリ食べたい!」というニーズに応える存在でした。しかし、近年では女性客やファミリー層を取り込む施策が増えており、客層が大きく変化しています。
例えば、こってり系に苦手意識を持つ女性向けに「こっさり」や「あっさり」メニューの導入、店内の清潔感向上など、以前とは異なる方向へのアプローチが目立っています。この変化により、従来のファンとのギャップが生じ、「天下一品っぽくなくなった」と感じる人も出てきています。
また、深夜営業の縮小やアルコール提供の減少など、従来の「〆ラーメン文化」からの離脱も、客層変化の大きな要因です。このように、時代に合わせた変化がファン心理にどう影響しているかは、見過ごせない要素です。
リピーター離れの原因とは?
天下一品には長年の固定ファンが多く存在しますが、近年では「久しぶりに行ったら満足感が薄かった」「味が薄くなった気がする」といった理由でリピートをやめる人も増えています。特に「価格に対する満足度」が下がっているという意見が多いのが特徴です。
たとえば、定食メニューが1,000円を超えることが当たり前になり、かつての“安くて腹いっぱい”というイメージが薄れてきています。それに加え、ラーメン1杯に対してのボリュームやサービス内容が追いついていないと感じる人もいます。
さらに、SNSや食べログなどでの評価が可視化される時代では、わずかな不満が拡散されやすくなっています。このように、情報の透明化が逆にリピーター離れを引き起こす一因となっているのです。
閉店を乗り越えるための施策と挑戦
新業態店舗の展開
天下一品は、従来のフランチャイズ型こってりラーメン専門店から一歩踏み出し、新しい業態へのチャレンジを始めています。その一例が、「天一×カフェ」や「酒場天一」などの異業種融合型店舗です。これらの店舗では、ラーメン以外の軽食やアルコールも提供し、昼夜問わず多様なニーズに対応しています。
新業態の店舗は主に都市部で展開され、若年層や女性客をターゲットにした内装デザインやサービスが特徴です。こうした店舗では、こってりラーメンに抵抗がある人にも気軽に足を運んでもらえるように配慮されています。
また、これまでの「ラーメン=男性向け」「こってり=重たい」というイメージを払拭することで、ブランドの再構築と新規顧客の獲得を目指しています。時代のニーズに合った新スタイルの提案は、今後の生き残り戦略として重要な柱となっていくでしょう。
コラボ商品や限定メニュー戦略
天下一品は、定期的に他企業とのコラボや季節限定メニューの展開を行っています。例えば、有名アニメやゲームとのコラボキャンペーンでは、限定グッズや特別メニューが用意され、SNSを中心に大きな話題となりました。
このような施策は、話題性によって新規顧客を呼び込むだけでなく、既存ファンのリピート意欲を刺激する効果もあります。また、期間限定メニューは「今しか食べられない」という希少性があり、売上アップにも直結しやすいのです。
近年では、「にんにくこってり」や「辛旨こってり」など、既存の“こってり”をベースにしたバリエーション展開も強化されています。これにより、一部の人にしか刺さらなかった味から、より幅広い層へのアプローチが可能となっています。
デジタル注文やアプリ活用の進化
飲食業界全体で進むデジタル化の流れに、天下一品も対応を進めています。公式アプリでは、スタンプカード機能やクーポン配信、混雑状況の確認などが可能になっており、リピーター向けの利便性が向上しています。
特に「こってりファン感謝祭」などのキャンペーンでは、アプリ限定特典が用意されており、若年層を中心にアプリ利用者が増加しています。また、一部店舗ではセルフオーダー端末やQRコード注文も導入されており、非接触・効率化が進められています。
これにより、注文ミスや待ち時間の短縮が実現し、店内オペレーションのスムーズ化にもつながっています。今後さらにアプリやデジタルサービスを強化することで、現代の顧客ニーズにより的確に応えていくと期待されています。
海外展開とその可能性
天下一品は過去に海外出店も試みており、現在ではハワイなどに店舗を構えています。日本食人気が高まっているアジアや北米では、「ヘルシーでユニークな日本のラーメン」として評価される可能性があります。
特に、「天下一品のこってり」は他のラーメンチェーンにはない独自の魅力があるため、差別化されたブランドとして展開する余地があります。ただし、海外展開には現地の味覚や食文化への適応、安定したスープ供給体制の整備など、課題も少なくありません。
それでも、日本国内での競争が激化する中で、成長市場を海外に求める動きは今後も加速していくと考えられます。成功すれば、国内ブランドの地位向上にもつながる重要な戦略です。
ロイヤルカスタマー育成の工夫
天下一品は、他のチェーンにはない「熱狂的ファン」が多いことでも知られています。こうしたロイヤルカスタマーを維持・拡大するために、本部はさまざまな施策を実施しています。
代表的なのが、「毎年10月1日の天下一品祭り」です。この日は全国の天一ファンが集まり、店舗には行列ができるほどの盛況ぶりを見せます。スタンプカードでどんぶりがもらえるキャンペーンなども、ファンの間では恒例行事となっています。
また、SNSを活用したキャンペーンや、店舗限定の裏メニュー提供など、ファンとの双方向コミュニケーションも重視されています。こうした取り組みが、長年の支持を維持する鍵となっているのです。
今後の天下一品とラーメン業界の行方
成長のカギは「こってり」の再定義?
天下一品の最大の魅力は、他にはない「こってり」スープです。しかし、その独自性が時代とともに「重すぎる」「健康に悪そう」といったマイナスのイメージを持たれるようになってきています。だからこそ、今こそ“こってり”の再定義が求められているのです。
具体的には、「重くて油っこい」という固定観念を払拭し、「濃厚だけど体にやさしい」や「食べごたえがあるけどヘルシー」といった新しい価値の創出が必要です。例えば、植物由来の成分を活用したスープや、発酵食品との組み合わせなど、健康と美味しさを両立させた“新・こってり”の開発が注目されています。
また、マーケティングにおいても、「懐かしさ」だけに頼るのではなく、現代的なライフスタイルに寄り添う形でブランディングを再構築していくことが、次なる成長のカギとなるでしょう。
独自ブランド力の再構築
天下一品が今後も生き残るためには、その「唯一無二の存在感」をさらに強化する必要があります。かつては「天一しかこの味は出せない」と言われていたほどの強烈なブランド力がありましたが、昨今は他のラーメンブランドやインスタント食品などでも似たような味が登場しています。
このような競合の増加の中で、再び“天下一品にしかない魅力”を打ち出すことが急務です。そのためには、味だけでなく、接客、内装、メニュー構成など、全体としてブランド体験を一新する努力が求められます。
また、若年層へのリーチを強化するために、YouTubeやTikTokなどの動画メディアを活用したプロモーション戦略も必要不可欠です。ブランドの世界観を視覚的に伝え、共感を得ることが、今の時代のファン獲得に直結するのです。
消費者の支持を取り戻すには?
一度離れてしまった消費者の心を取り戻すには、「やっぱり天一は最高だ」と感じさせる体験が必要です。そのために、まず重要なのは“味の安定化”です。どの店舗でも同じクオリティのこってりスープが楽しめるという安心感は、ファンのリピートに直結します。
さらに、価格と満足度のバランスを見直すことも重要です。現在の価格設定に対して、量・味・サービスのどれもが納得できる内容でなければ、消費者は離れていってしまいます。定食メニューやランチ限定セットの充実、ボリューム調整のオプション化など、柔軟な対応が鍵となります。
また、顧客の声を反映した改善を積極的に行い、「変わった」ことを伝える広報活動も欠かせません。昔からのファンにも、新しい時代のファンにも寄り添ったサービスを提供することで、再び強い支持を得ることができるでしょう。
飲食業界の中での天下一品のポジション
日本のラーメン業界は、常に新しいスタイルやトレンドが生まれる非常に競争の激しい市場です。その中で天下一品は、「定番の安心感」と「クセになる中毒性」の両方を持った稀有な存在です。しかし、そのポジションを維持し続けるのは簡単ではありません。
一蘭のようなシステム化された高価格帯のブランド、家系ラーメンのようなパンチのあるラーメン、はやし田のような洗練された味わい系…ライバルは多岐に渡ります。そんな中で天下一品は、「昭和から続く安心の味」としてのアイデンティティを大切にしながらも、柔軟に現代化していく必要があります。
たとえば、スープの選択肢を増やす、ベジタリアン対応メニューの導入、アルコール提供の復活など、独自の魅力を活かしつつ新しい価値を提供することで、業界内での独自ポジションを確立できます。
次の10年を見据えた戦略とは
天下一品がこの先10年、生き残り、成長していくためには、短期的な売上アップだけでなく、長期的なブランド価値の向上を見据えた戦略が必要です。そのためには、以下のような方向性が考えられます。
| 戦略分野 | 具体的な施策 |
|---|---|
| 商品開発 | 新こってりスープ、健康志向メニュー開発 |
| 顧客戦略 | アプリ強化、ロイヤル顧客向け特典 |
| 店舗戦略 | 都市型コンパクト店舗、多業態融合 |
| 海外展開 | アジア圏への再進出、現地味調整 |
| ブランディング | SNS戦略、動画プロモーション強化 |
こうした多角的な戦略を同時進行で展開することで、単なる“昔ながらのラーメンチェーン”から、“進化するラーメン文化の発信基地”へと進化することが可能です。
まとめ
天下一品の閉店ラッシュには、さまざまな背景がありました。地方店舗を中心とした閉店の増加は、単なる人気の低下ではなく、人手不足や原材料の高騰、フランチャイズ契約の見直しといった経営的な問題が複雑に絡み合った結果です。また、ラーメン業界全体もトレンドの変化や健康志向の高まりの中で、生き残りをかけた変革を迫られています。
そんな中で天下一品は、新業態の展開やデジタル化、限定メニュー戦略、さらには海外展開といった前向きな施策に取り組んでいます。今後は、「こってり」という唯一無二の価値を再定義し、時代に合わせたブランディングを進めることで、さらなる支持を集めていくことが求められるでしょう。
ラーメン業界は常に変化し続けています。その中で“変わらない良さ”と“進化する姿勢”を両立できるかどうかが、天下一品にとっての未来を決めるカギとなるのです。

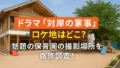
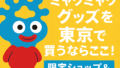
コメント