「昔はよく見かけたのに、最近は全然見ないよね。」
街の商業施設から、観光地のアイスショップまで、かつて多くの人に親しまれていた「コールドストーン・クリーマリー」。歌う店員、目の前で作るライブ感、カラフルで贅沢なアイス。そんな唯一無二の体験が話題となり、日本中で一世を風靡しました。
しかし今、なぜこんなにも閉店が相次いでいるのでしょうか?
この記事では、コールドストーンが辿った栄光と苦境、そして今後の可能性について、データや口コミ、トレンドをもとに徹底解説します。なぜ“あの味”が遠ざかってしまったのか、その理由が見えてきます。
コールドストーンとは?日本上陸から現在までの歩み
アメリカ発の人気アイスブランドが日本に上陸
コールドストーン・クリーマリー(Cold Stone Creamery)は、アメリカ・アリゾナ州で1988年に誕生したアイスクリームブランドです。「エンターテイメント性のあるアイスショップ」として注目を集め、注文ごとにアイスクリームとトッピングを冷たい石板(コールドストーン)の上で混ぜ合わせるスタイルが特徴です。
日本には2005年に初上陸。第1号店は東京・六本木ヒルズにオープンし、大きな話題を呼びました。そのユニークな提供スタイルとアメリカンな雰囲気、そして味の濃厚さが、当時の日本では新鮮に映ったのです。
当初は日本人の間でも“ちょっと特別なスイーツ”として高評価を受け、SNSやテレビでもたびたび取り上げられました。特に若年層やカップルに人気で、記念日やお出かけのついでに立ち寄る人が多く見られました。
このようにして、コールドストーンは「アイスクリーム=手軽なおやつ」という既成概念を覆す存在として、日本でもその名を広めていきました。
「歌う店員」で話題!ユニークな接客スタイルとは
コールドストーンの代名詞とも言えるのが、スタッフがアイスを作りながら歌を歌ってくれるというエンターテイメント接客です。これはアメリカ本国でも同様のスタイルがあり、日本でもその文化を取り入れた形です。
お客さんの前で明るく元気に歌う姿は、多くの来店者の記憶に残り、口コミやSNSを通じて話題となりました。特に初めて体験した人には「こんなに楽しいアイス屋さんがあるなんて!」という驚きがあったようです。
また、注文時にリクエストすると、誕生日ソングやポップソングを披露してくれるサービスもあり、記念日やサプライズ演出としても人気でした。こうした体験型のサービスは、他のアイスクリームチェーンにはない魅力として長く親しまれてきました。
しかし、スタッフの負担や店舗によるバラつきもあったため、次第にこのサービスを実施しない店舗も増えていくことになります。
オープン当初の熱狂と行列の秘密
2005年の六本木ヒルズ出店以降、コールドストーンは瞬く間に話題となり、テレビや雑誌での特集も相次ぎました。特に当時の日本では「カスタムメイドのアイス」や「歌う店員」といったコンセプトが新しく、若者の注目を集めました。
オープン直後には行列ができる店舗も多く、土日には1時間以上待つことも珍しくありませんでした。その理由のひとつが「その場で混ぜるライブ感」と「できたての美味しさ」にあります。
また、店内で提供されるアイスは“ラブイット”や“ライクイット”など独自のサイズ呼称が使われることも話題に。エンタメ感満載の演出が、日本の消費者に「新しい体験」を提供し続けたのです。
しかし、ブームは一時的なものであることも多く、後の章で紹介する通り、人気のピークはそう長くは続きませんでした。
どのように全国展開していったのか
六本木の成功を受けて、コールドストーンは関東を中心に出店を拡大し、徐々に全国へと広がっていきました。商業施設内のテナントとして出店するスタイルが多く、特に若年層が集まる都市部での出店が目立ちました。
2008年頃には全国で30店舗以上にまで拡大し、北海道から九州まで幅広く展開していきました。その中には観光地や空港内の店舗もあり、「旅の思い出」としての需要にも応える戦略を取っていました。
ただし、出店には大きな設備投資が必要であることや、アイスの品質維持のためのコストも高く、採算が取れないエリアでは閉店も相次ぐようになります。
このように急拡大と撤退を繰り返す中で、ブランドイメージに揺らぎが生まれていくことになります。
どこにでもある存在から“特別感”が薄れた?
当初は「ここでしか食べられない」という特別感があったコールドストーンですが、出店が増えるにつれ、「どこでも食べられる普通のスイーツ」へと印象が変わっていきました。
また、エンタメ性や高級感を維持するための努力が見られなくなったという声もあります。たとえば、歌を歌わないスタッフが増えたり、混ぜるパフォーマンスが簡略化されたりと、当初の感動体験が失われたことも一因です。
さらに、他のスイーツブランドが次々と新しい体験型サービスや低価格・高品質の商品を展開し始めたことで、コールドストーンは次第に“時代遅れ”と見なされるようになりました。
その結果、特別感や高揚感が薄れ、リピートする理由が見出しにくくなってしまったのです。
なぜ閉店が相次いでいるのか?コールドストーンの現状分析
店舗数はどれくらい減った?閉店の実態データ
コールドストーンは日本に上陸した2005年から数年で急速に店舗数を増やしましたが、現在ではその数は大幅に減少しています。ピーク時には日本国内で30店舗以上展開していたものの、2020年代に入ってからは閉店が相次ぎ、現在ではわずか数店舗しか営業していません。
この急減の背景には、単なる一時的なブームだったことに加え、継続的な売上維持が困難だったという実情があります。特に商業施設内の店舗は集客力に大きく左右されやすく、施設のリニューアルや集客低迷といった外部要因で閉店に追い込まれたケースも多く見られました。
また、フランチャイズ展開による出店も多かったため、採算が合わない場合の撤退も早く、経営体力のある大手ブランドと比べて撤退判断が迅速だったとも言えます。
閉店店舗の多さは、ブランドに対する信頼感の低下にもつながり、「あそこも無くなった」「もう見かけない」といった声が増えることで、さらに来店意欲が減るという悪循環に陥りました。
コロナ禍の影響は?売上と客足の激減
コロナウイルスの感染拡大は、飲食業界全体に大打撃を与えましたが、コールドストーンのような「対面接客」「商業施設立地」「非日常体験型」の業態にとっては特に厳しい状況となりました。
まず、店舗の多くが大型ショッピングモール内にあるため、緊急事態宣言中やまん延防止期間中には施設そのものが休業、または時短営業を余儀なくされました。結果的に、自然と人の流れが減り、売上も激減しました。
さらに、コールドストーンの売りであった「店員が目の前で混ぜてくれる」「歌ってくれる」といった接客スタイルは、コロナ禍では“密”を連想させてしまい、敬遠される要因にもなってしまったのです。
加えて、感染防止のためにマスクを着用したままの接客が必要となり、パフォーマンス性が大きく損なわれました。このように、ブランドの強みであった「体験価値」が逆に足かせとなってしまったのは、大きな痛手だったと言えるでしょう。
高価格帯のアイスは日本市場に合わなかった?
コールドストーンのアイスは、いわゆる「プレミアムスイーツ」のカテゴリに属します。トッピングを自由に選べる反面、1つの商品にかかる価格は700円〜1,000円程度になることが多く、決して安くはありません。
この価格帯は、日本のスイーツ市場ではやや高めに設定されており、日常的に利用するにはハードルが高いと感じる人も多かったようです。たとえば、同じアイスジャンルで人気のサーティワンは、手頃な価格とお得なキャンペーンを打ち出し、家族連れにも愛されています。
対照的に、コールドストーンはイベント性の強いスイーツであったため、日常の中で「ついでに食べる」という行動には結びつきにくかったのです。
また、物価高や消費税増税といった経済的な背景もあり、消費者が「プチ贅沢」よりも「コスパの良さ」を重視する傾向にシフトしていったことも、売上減の一因と考えられます。
スイーツトレンドの変化と競合の台頭
スイーツ業界はトレンドの移り変わりが激しい業界です。かつてはアイスクリームブームがありましたが、次第にタピオカ、チーズティー、パンケーキ、韓国スイーツなどがブームを巻き起こし、コールドストーンのような「昔ながらの洋風スイーツ」は話題になりにくくなってきました。
また、InstagramやTikTokを通じて視覚的に映えるスイーツが流行の中心となる中で、コールドストーンの演出は一時期ほどの“新鮮さ”を感じさせなくなったのも大きいです。
加えて、個人経営のオシャレなアイスクリーム店や、ヴィーガン対応など健康志向に対応したブランドも増え、多様化する消費者ニーズに十分応えられなかった点も影響しています。
時代の流れに乗るには、常に「アップデート」が求められるスイーツ業界。その変化に柔軟に対応できなかったことが、競合との差を広げる要因となりました。
立地戦略の失敗?ターゲット層とのズレ
コールドストーンは、主に都市部の大型商業施設や観光地への出店が多く、若年層やカップル層をターゲットにしていました。しかし、それがかえって「通りがかりで買う」スタイルには不向きとなり、定期的な来店が望めない状況に。
また、オフィス街や住宅街にはほとんど出店しておらず、リピーターを獲得するための戦略が弱かったといえます。結果として、観光目的やお出かけの際の“たまにの贅沢”という立ち位置に留まり、安定した売上を確保しにくい構造でした。
さらに、駅直結などの利便性の高い場所でなく、施設の奥まったエリアや上階など、視認性に乏しい場所での出店が多かった点も課題のひとつです。
立地選定がターゲット層の行動動線と一致しなかったことで、せっかくのブランド力を活かしきれなかったのは非常にもったいないポイントだったと言えるでしょう。
SNSや口コミで見る「コールドストーン離れ」の兆候
昔は「インスタ映え」だったのに今は…
かつてコールドストーンは、SNSで「インスタ映えするアイス」として若者の間で高い人気を誇っていました。カラフルなトッピング、カップやワッフルボウルのビジュアル、さらには歌うスタッフとの動画まで、投稿するだけで「話題になる」存在でした。
特に2010年代前半は、Instagramが急成長した時期と重なり、スイーツ写真がバズる要素として重要視されていたため、コールドストーンのビジュアルは注目を集めやすかったのです。
しかし、近年ではSNSにおけるスイーツ投稿の流行が変化しています。「映える」だけでなく「珍しさ」や「テーマ性」、「ストーリー性」が重視されるようになり、従来のコールドストーンのビジュアルは“見慣れたもの”として新鮮味が薄れてしまいました。
また、見た目の派手さで勝負する競合ブランドが次々と現れたことにより、かつてのような圧倒的な存在感を発揮することが難しくなってきたのです。
SNSでの話題性が減った理由
コールドストーンのSNSにおける投稿数やハッシュタグの使用頻度を見ても、近年は明らかに減少傾向にあります。その理由は、単に流行が終わったからというよりも、「新しい話題を提供できていない」ことにあります。
他ブランドが次々と新商品やコラボ商品を投入し、常にトレンドを生み出しているのに対し、コールドストーンは定番メニューの継続が中心。目新しさが感じられないため、ユーザーがわざわざ投稿するインセンティブが生まれにくくなったのです。
また、公式アカウントの更新頻度や情報発信のトーンにも課題があり、「コールドストーンのSNSはつまらない」「発信が遅れている」といった声も一部で見られます。
SNS時代においては、ブランド側の発信力も非常に重要です。その点で後れを取ったことが、話題性の低下につながったと考えられます。
リピーターが減少した背景とは
コールドストーンは一度体験すると満足感の高いブランドですが、それがリピートに結びつかないという課題も抱えていました。理由の一つはやはり価格帯。700〜1,000円近くするアイスは、日常的に何度も食べられる価格ではありません。
また、体験型スイーツという特性上、「初めてのワクワク」が一度きりの体験で終わってしまうことも問題です。何度食べても新鮮さが感じられない、という点がリピーターの減少に直結しています。
さらに、全国展開されていたとはいえ、主要都市や大型施設にしか店舗がないため、近くにお店がない人にとっては“気軽に行ける場所”ではなかったのです。
こうしたアクセスの悪さや価格の高さ、体験の一過性といった複数の要素が絡み合い、リピーターの獲得が難しい状況になってしまいました。
口コミで目立つネガティブな声
食べログやGoogleレビュー、Twitter(現X)などの口コミを調べると、ポジティブな意見と同時にネガティブな声も目立ちます。
よく見られる意見としては以下のようなものがあります。
- 「味が甘すぎてくどい」
- 「価格に対して満足度が低い」
- 「混ぜ方が雑だった」
- 「接客にばらつきがある」
- 「昔ほどワクワクしなくなった」
特に「接客」に関する評価は店舗ごとの差が大きく、店によっては「歌ってくれなかった」「混ぜるだけで無愛想だった」など、エンターテインメント性が失われているという声が目立ちます。
こうした口コミは拡散力の強いSNSを通じてすぐに広まり、来店を検討している人の足を遠ざけてしまう要因となります。
若年層の支持が薄れている?
かつてコールドストーンの主なターゲットは、10代後半から20代の若者層でした。しかし、今の若者はより“コスパ重視”かつ“映えの進化系”を求める傾向にあり、シンプルに「高い」「普通」と感じるようになってしまっています。
また、最近の若者は「健康志向」や「ヴィーガン対応」などにも敏感です。その点で、コールドストーンのラインナップは少々時代遅れに感じられることもあります。
結果として、「わざわざ行く理由がない」「友達に勧めるほどでもない」と感じる若者が増え、情報の拡散力が弱まっているのが現状です。
ブランドが若年層に支持されなくなったとき、リブランディングやプロモーションの再構築が急務となりますが、コールドストーンはその動きがやや鈍かったと言えるでしょう。
他ブランドとの比較で見えてくるコールドストーンの課題
サーティワンとの違いと共通点
アイスクリームチェーンといえば、日本国内で圧倒的な知名度を誇るのが「サーティワンアイスクリーム(Baskin-Robbins)」です。コールドストーンとよく比較される存在でもあります。
サーティワンは、「毎日違う味が楽しめる」ことを売りにしており、季節限定フレーバーの豊富さや、お手頃な価格帯が魅力です。特にファミリー層に人気があり、全国のあらゆるエリアに店舗があるため、日常的に利用しやすいのが強みとなっています。
一方でコールドストーンは、目の前でアイスを混ぜるライブパフォーマンスが特徴で、「体験型スイーツ」としてのポジションを築いていました。しかし、体験の新鮮さが一度きりになりやすく、サーティワンのように日常に溶け込む存在にはなれなかったのです。
両者の共通点は「アイス専門店」であることと、「トッピングやフレーバーで個性を出している」ことですが、その先の戦略がまったく異なります。コールドストーンは特別な体験を重視しすぎたことで、日常利用の機会を失ったと言えるでしょう。
ゴディバやハーゲンダッツと比べてどう?
もう一つ比較されるのが、高級路線で展開する「ゴディバ」や「ハーゲンダッツ」といったブランドです。これらは価格帯がコールドストーンと同じかそれ以上でありながら、安定した人気を保っています。
ゴディバは「チョコレートの高級ブランド」としてのブランド力が強く、ギフト需要にも対応しているのが特徴です。カフェ業態にも展開しており、スイーツ以外の領域でも集客しています。
ハーゲンダッツはコンビニやスーパーで手に入る「ご褒美アイス」として、手軽に楽しめる高級感を提供。さらに、定期的な新作投入や、SNS映えを意識したマーケティングにも力を入れています。
対して、コールドストーンは「中途半端な高級感」に陥っていた印象があります。店舗でしか味わえない限定感がある反面、ブランドイメージが十分に浸透しておらず、「お金を出してまで食べる価値があるのか」という疑問を持たれることもあったのです。
成功しているスイーツブランドの特徴
成功しているスイーツブランドには、いくつかの共通点があります。
- 明確なコンセプトがある
例:ハーゲンダッツ=「贅沢」、サーティワン=「選ぶ楽しさ」 - 定期的な新商品・イベントを展開
例:スターバックスのフラペチーノ、ミスドのコラボシリーズ - SNS戦略がうまい
目を引くビジュアル、投稿キャンペーン、インフルエンサーとの連携など - 手に取りやすい価格帯と立地
「いつでもどこでも買える」ことが、ブランドの定着につながる - 時代のニーズを取り込む柔軟さ
ビーガン対応、アレルゲン対応、健康志向メニューの導入
コールドストーンは、初期には「楽しいアイス体験」という明確な強みがありましたが、それ以外の要素でこれらに追いつけなかった点が、ブランド力に差を生む結果となりました。
競合が強い都心での苦戦
コールドストーンは多くの場合、都心部の商業施設に店舗を構えていました。たしかに人通りは多いのですが、競合もひしめく場所です。話題性のあるカフェ、行列のできるスイーツショップ、海外から上陸した新ブランドなど、激しい競争にさらされていたのです。
こうしたエリアでは、目新しさや話題性がないとすぐに埋もれてしまいます。コールドストーンは一時的に話題をさらったものの、新たな顧客を呼び込む施策が少なく、既存ファンに頼る形が続きました。
また、価格帯も高めでリピーターを作りづらかったため、近隣の競合店に流れてしまうケースも少なくなかったようです。競争の激しい都心で生き残るには、常に「次の一手」を打つ柔軟さが求められます。
なぜリブランディングに成功できなかったのか
コールドストーンが低迷を続ける中で、「リブランディング」の必要性が何度も叫ばれてきました。しかし、結果としてそれが十分に機能することはありませんでした。
たとえば、歌う接客を控えるようになった後も、それに代わる新しい体験価値やサービスが明確に打ち出されなかった点が挙げられます。また、メニュー刷新や期間限定商品、コラボ企画なども少なく、SNSで話題になるような展開も限定的でした。
他ブランドが「常に変化し続ける」ことで注目を集めていたのに対し、コールドストーンは「変わらないこと」がかえって足かせになってしまったのです。
ブランドとして再び脚光を浴びるためには、原点回帰だけでなく、時代に即した再構築が必要でした。しかし、それを推し進めるだけの戦略やスピード感が足りなかったことが、リブランディング失敗の要因と考えられます。
コールドストーンの今後と可能性
今も愛されているメニューは?
閉店が続いているとはいえ、コールドストーンには今でも根強いファンが存在し、特定のメニューに対する高い評価も残っています。特に人気があるのは以下のような定番メニューです。
- ストロベリーショートケーキセレナーデ
- チーズケーキファンタジー
- チョコレートデヴォーション
- バナナキャラメルクランチ
- グリーンティーパラダイス(抹茶系)
これらのメニューは、甘さのバランスが良く、トッピングの組み合わせも絶妙だと高評価です。また、季節限定で登場するフレーバーにも熱心なファンがついており、「あの味が忘れられないからまた食べに行く」という動機にもなっています。
一部の常連客にとっては、「高くてもまた食べたくなる味」として特別な存在であり、味そのものには今でも十分な競争力があるのです。今後のブランド再構築においても、この「記憶に残る味」は大きな武器となるでしょう。
テイクアウト・デリバリーへの対応は?
近年、飲食業界全体で需要が拡大しているのが「テイクアウト」や「デリバリー」への対応です。特にコロナ禍以降は、実店舗に行く代わりに家で楽しめるサービスが急速に拡大しています。
コールドストーンも一部店舗でUber Eatsや出前館などのデリバリーサービスに対応し始めています。ただし、アイスクリームという商品の特性上、配達中に溶けてしまうリスクが高く、品質維持の面で課題が多いのも事実です。
また、テイクアウト用の専用パッケージや冷凍保存用アイスの展開がやや限定的で、まだ本格的に展開しきれていない印象があります。
今後は、店内での体験型サービスだけに頼るのではなく、家庭でも楽しめる形へのシフトが必要でしょう。冷凍技術や特殊容器の導入、ECサイトでの販売など、多角的な販売チャネルの整備が進めば、新たな需要を掘り起こせる可能性があります。
海外展開での成功事例はある?
コールドストーンは、実は世界中に展開しているグローバルブランドです。アメリカ本国はもちろん、アジア圏でも台湾、フィリピン、韓国、中国などに店舗を構え、現地のスイーツ市場に合わせたメニューで展開しています。
特に台湾では、若年層を中心に人気を集めており、日本よりも高評価を得ている店舗もあるほどです。韓国でもカフェ文化の一環として一定の支持を得ており、季節限定フレーバーや独自のコラボレーションが話題になっています。
このように、日本での苦戦とは対照的に、他国ではローカライズや柔軟なサービス対応によってうまくブランド展開しているケースがあります。
つまり、コールドストーンは「アイスの味そのもの」に問題があるのではなく、「日本市場での戦略と運営体制」に課題があったことを示しています。成功事例を参考に、日本でも再び立て直す余地は十分に残されているのです。
今後の復活の鍵となるポイント
コールドストーンが日本市場で復活を遂げるには、いくつかの「鍵」が存在します。
- 体験価値の再定義
単なる「混ぜるアイス」から、もっと感動体験へと進化させる演出が求められます。 - 価格帯と商品の見直し
ミニサイズやセット販売など、日常使いしやすいメニューの開発が重要です。 - SNS戦略の強化
トレンドに乗った発信、映えるメニュー開発、インフルエンサーとの連携などで再注目を集める必要があります。 - コラボレーションの展開
アニメ、キャラクター、アーティストなどとのコラボは集客効果が高く、ブームを呼ぶ可能性があります。 - 通販・冷凍販売の強化
店舗数が減っている今こそ、オンライン販売を拡充することで新しいファン層を獲得できます。
これらを総合的に実施することで、再び「話題のスイーツブランド」として立ち位置を取り戻すチャンスはあるでしょう。
消費者が求める「変化」とは?
現在の消費者は、単に「美味しい」だけでなく、そこにどんな価値やストーリーがあるかを重視しています。たとえば、「映えるだけでなく健康にも配慮されている」「サステナブルな取り組みがある」「推しとコラボしている」など、共感できる要素があるブランドが選ばれやすい時代です。
コールドストーンも、こうした新しい消費者心理に対応する必要があります。たとえば、低糖質アイスの開発、環境にやさしい素材の使用、地域限定フレーバーの展開など、時代に寄り添った取り組みを打ち出すことが求められるでしょう。
また、これまでの「アメリカ風」という演出が時代に合わなくなっている可能性もあるため、より多様な世界観を取り入れる工夫も必要です。消費者は「変化」を求めています。その変化に応える柔軟さとスピードが、今後のコールドストーンの命運を左右すると言えます。
まとめ:コールドストーンの「今」と「これから」を見つめ直す
かつて「歌って混ぜるエンタメ系アイス」として日本中で話題となったコールドストーン・クリーマリー。しかし、次第に話題性を失い、店舗の大幅減少、そして消費者の関心離れが進んでしまいました。その原因は一時的なブーム依存、価格帯の高さ、トレンドへの対応力不足、SNS戦略の遅れなど、さまざまな要因が複雑に絡んでいます。
一方で、味のクオリティや一部商品の根強い人気、海外での成功例を見ると、ブランドそのものにはまだ可能性が残されています。今後、体験型サービスの再定義やSNS施策、コラボ戦略、そして新しい販売チャネルの開拓などを通じて、再び注目を集めるチャンスは十分にあるでしょう。
アイスクリームは、単なるスイーツではなく、人の心を動かす「体験」でもあります。コールドストーンがかつての輝きを取り戻すには、その原点をもう一度見つめ直し、今の時代にふさわしい価値を提供する必要があるのです。

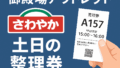
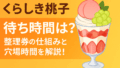
コメント